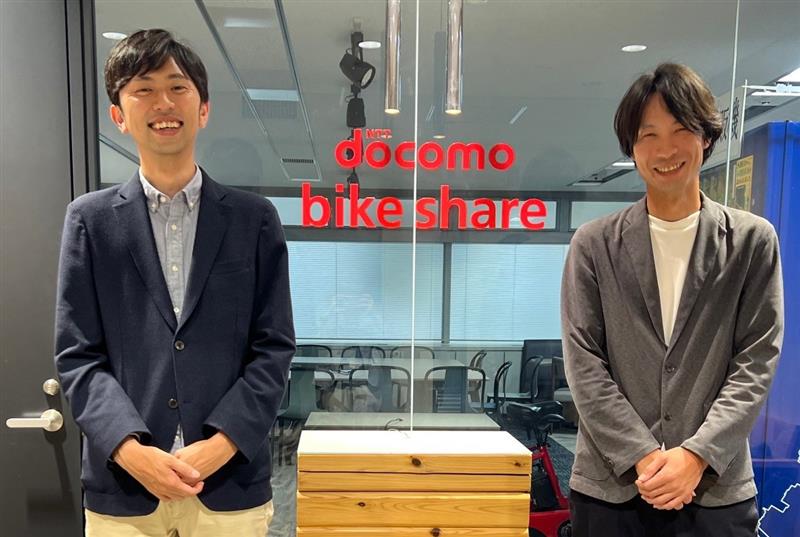お客様の声
<株式会社ドコモ・バイクシェア>
モビリティUX部
部長 石橋 毅一 様
モビリティUX部
モビリティUX担当課長 塩谷 圭一郎 様
──ドコモ・バイクシェアで展開されているサービスについて教えてください。

モビリティUX部
部長 石橋 毅一 様
石橋様
弊社ドコモ・バイクシェアでは、全国でシェアサイクルを運営しております。ちょうどこの2月で10周年を迎えまして、サービスを開始してから多くのお客様にご利用いただいています。昨年には累計のご利用回数が1億回を超えました。東京でも弊社の赤い自転車を見かける機会も多くなってきているかと思いますが、さまざまな地方都市でもご利用いただいています。大阪や仙台、また現在、新型モビリティの実証実験を行っている広島など、地方の都市部を含む全国61のエリア(※2025年4月末時点)でサービスを展開しています。
シェアサイクルの用途としては、通勤・通学など日常の移動でご使用いただくケースが多いですが、エリアによっては観光用途でのご利用も多いです。名所を回るために自転車を1日中ご利用いただくなど、ユースケースはエリアの特徴で変わってきます。
弊社の直営型でシェアサイクル事業を展開するモデルと、我々のシステムを活用して事業者様にシェアサイクル事業を展開いただく「ASP」と呼ばれるモデルで運営しているケースがあります。
──最近では本当に多くの場所で赤いシェアサイクルを見かけます。
石橋様
我々のサービスは、ラストワンマイルといわれる移動手段としての役割を果たしています。電車の駅やバス停などから自宅やオフィスへの移動などにご利用いただくケースも多いので、多くの人が集まる場所にポートを設置し、移動の利便性を高めています。累計のご利用回数が1億回を超えましたが、特にコロナ禍以降の三密回避の動きの中で需要が高まりました。こういった社会的な背景も相まってシェアサイクルの市場自体が拡大してきています。
──現在、広島で新型モビリティ導入に向けた実証実験を実施されています。新型モビリティの特徴を教えてください。
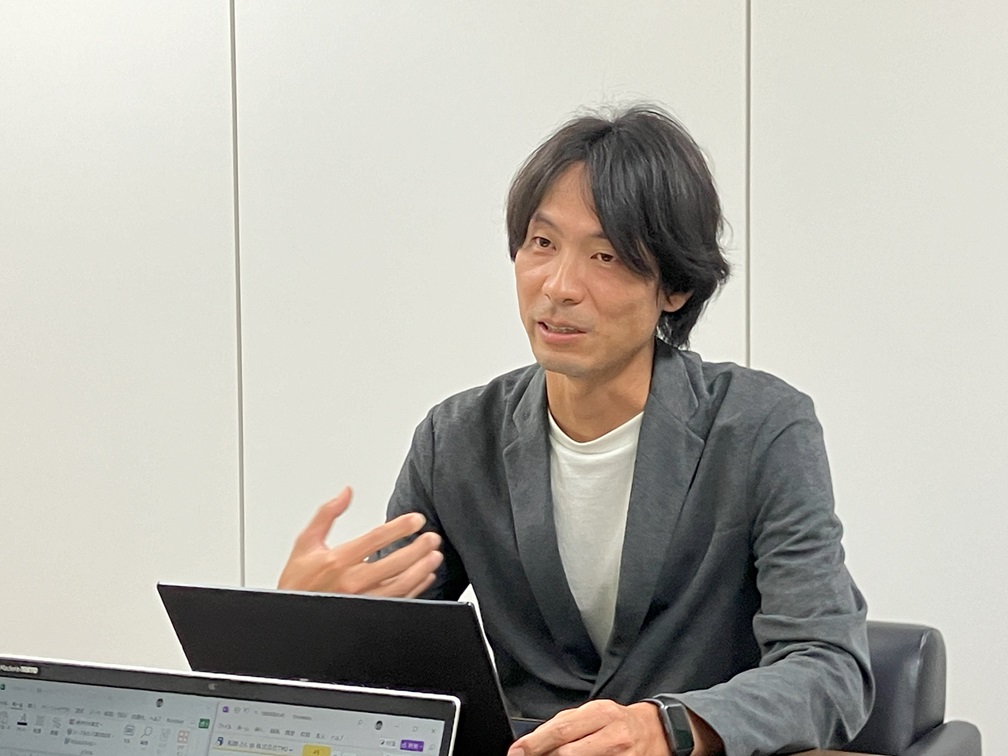
モビリティUX担当課長
塩谷 圭一郎 様
塩谷様
新型モビリティは特定小型原付という新しい区分の乗り物で、自転車ではありません。これまでは基本的に自転車をシェアリングさせていただいてきましたが、やはり「暑い日に自転車をこぎたくない」「坂道が大変」といった一定のハードルがあることは認識していました。サービスの利便性や快適性をさらに高めてユーザー様のニーズにお応えするということで、足でこがなくても利用できる特定小型原付の導入に至りました。
車両に関してはさまざまな候補の中から選定を進めていく中で、一般の方が乗り慣れている形状を意識して、最終的に自転車タイプを採用することになりました。座って操作するだけで前に進みますが、自転車と同じ感覚で扱える車両を選定していますので、幅広いユーザーの方にご利用いただけると考えています。
今回の車両の選定において、さまざまなモビリティを試乗しましたが、特定小型原付の中で一番大きなタイヤサイズで、非常に安定感のあるモビリティを採用できたと考えています。メーカーであるYADEA社もモビリティの生産と市場投入において信頼性が高く、ユーザー様にも安心してご利用いただけると考えています。
石橋様
最近は夏場だとかなり暑いので、自転車をこぎたくないというお客様の声もあります。シェアサイクルの利用回数の傾向を見ていると、もっとも利用が伸びる春先や秋口に比べ、夏場は減少傾向になります。そんな昨今の暑い夏でも、こがずに楽に乗れる新型モビリティを移動手段のひとつとして活用していただきたいですね。
──新型モビリティは歩道走行不可の運用とされていますが、その理由は?
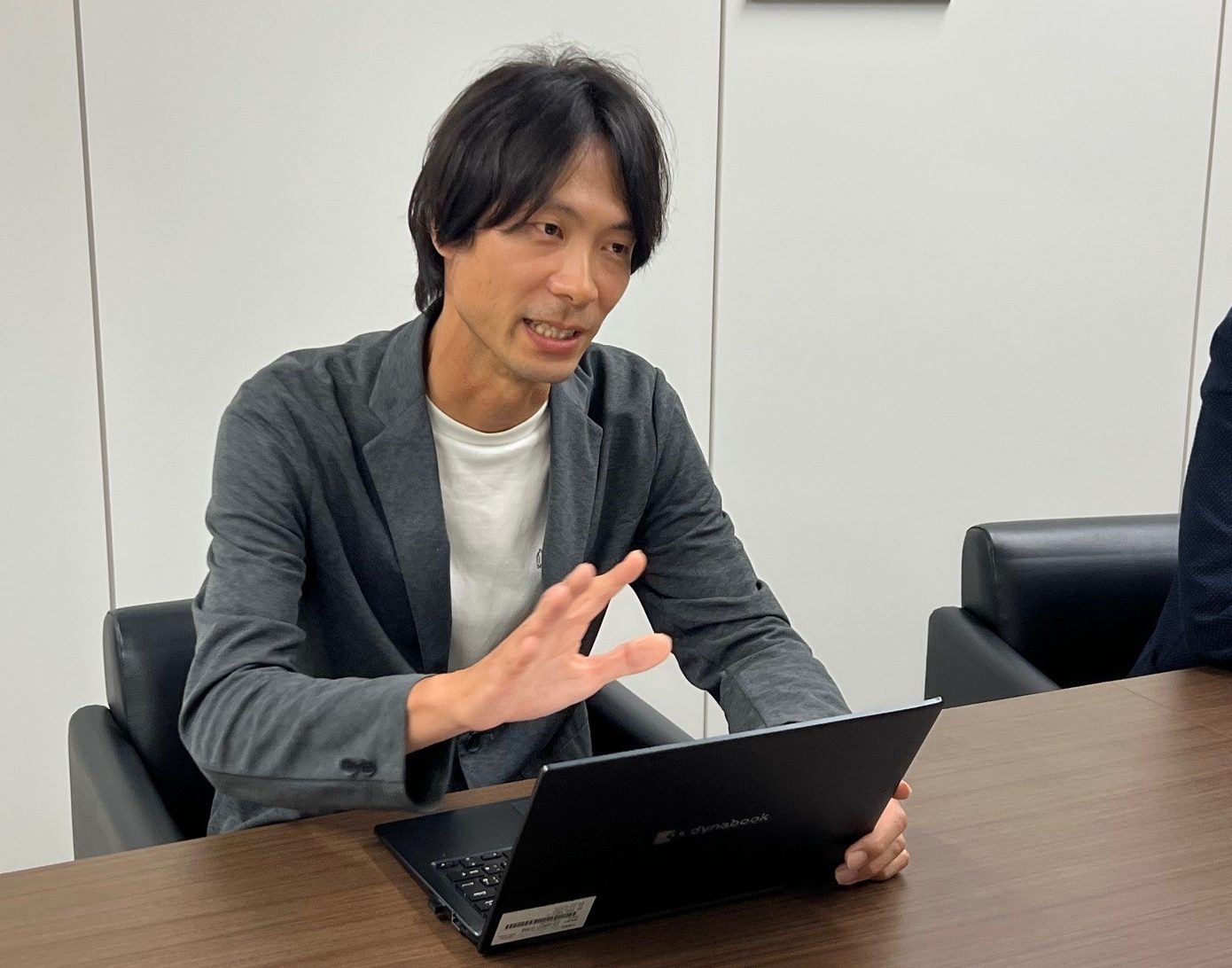
塩谷様
特定小型原付の車両の中には速度を6キロに制限して歩道を走行できる「特例モード」を備えた車両もありますが、利用時のモード切り替えが難しかったり、速度を制限せずに歩道を走行してしまうケースも指摘されています。こういった背景から、我々はあえて歩道を走行できるモードを非搭載としました。「交通空間を安全に」と強く訴えたい思いがあります。
──新型モビリティの実証実験の概要を教えてください。
塩谷様
今回の実証実験は、新型モビリティの安全性が世の中に受け入れられ、ユーザー様に快適にご利用いただけるかを見極めることが目的です。先ほども少し触れましたが、特定小型原付に対しては、ユーザー様の交通ルールへの理解が不十分であったり、交通マナーが守られていなかったりする事から安全面で指摘を受けていることも事実です。ただ、便利なものであることは間違いないですし、我々としてはしっかりユーザー様に交通ルールをご理解いただき、マナーを遵守してサービスをご利用いただきたいと考えています。そのために、運転免許証の所持確認、より実践的な交通ルールテストの実施に加え、車両後輪部分に「この車両が歩道走行不可である」旨を記載したステッカーを貼り付けるなど、より安全に使っていただくためにシェアリング事業者としての対策を講じています。
実証実験では、ユーザー様に新型モビリティの安全性が受け入れられ、快適にご利用いただけるかどうかを見極めたいと考えています。
広島では我々の電動自転車のサービスをすでに展開しており、自治体様の向き合い方も含めて導入しやすい状況でした。通勤通学や観光利用のニーズがあり、市電を含めたさまざまなモビリティが混在している点や、エリアの規模的にも検証を行うのに適した場所と考えています。
実施は今年9月までの約半年を予定しており、無料でお試しいただいたり、イベントに参加してお披露目していきたいと考えています。さまざまな施策を通じて、我々の取り組みがどの程度浸透していくか、安心安全と思っていただけるかなど、ユーザー様の声をしっかり拾っていきたいと考えています。その中で見えてくる課題を次のステップに活かして改善していきたいと考えています。
──今回の実証実験のお問い合わせ対応などを弊社TMJにお任せいただいています。過去に別業務を委託いただいている背景もあると思いますが、今回の実証実験のお客様対応においても弊社サービスを採用いただけた理由を教えてください。

石橋様
特定小型原付自体がまだ認知されていないところもありますので、お客様対応やフォローはしっかり行っていくべきと考えていました。(TMJには)すでに弊社の法人会員様向けのコールセンターも受けていただいている実績がございますし、さまざまなモビリティサービスの対応に特化した専門の部門で対応いただける点が非常に安心感がありました。
運転免許証の認証で使用されるeKYCの運用などでも実績があることは存じ上げておりましたし、さまざまなサポートを含めて安心してお任せできると考えました。実際、今回の実証実験の趣旨をご理解いただいて、我々の期待値以上に柔軟にご対応いただけている印象です。
──ご利用者様からの反応はどのようなものがありましたか。またTMJの対応に対する要望などはありますか。
石橋様
これまでのところお客様の反応は概ねイメージ通りですが、中には熱心なお客様もいらっしゃいまして、何度も新型モビリティに乗っていただいて既存の自転車との比較をいただいたり、広島の街のさまざまな場所を走って良かった点や課題点をお伝えいただいたりということもありました。
塩谷様
さまざまな声を拾っていただいて共有いただいたり、真摯にユーザー様に向き合っていただいていると思います。我々の方にいただいた声の中には、コールセンターの方のお名前をご存知になられていて、その方に「よろしくお伝えください」とおっしゃるケースもありました。ユーザー様にしっかりと向き合っていただいていると思っています。ユーザー様と接点のある場所ですので、引き続きより良いサービスにつながる改善の提案もいただけると助かります。
──貴社のシステムを導入してシェアサイクル事業を行う事業者の方々についてメッセージをいただけますか。
塩谷様
新型電動モビリティを軸に移動手段の多様化が実現できることを期待しています。お客様の目的地に応じてモビリティの使い分けができるため、移動自体の体験価値も上がるものと考えています。
今回、ユーザー様にとってより便利にご利用いただける仕組みを導入できました。これまで以上に自治体の皆様や弊社のシステムを活用して街づくりを担われる事業者様にご活用いただけると考えています。
──最後にユーザーの方々にもメッセージをお願いします。
石橋様
我々としては、ご利用いただくお客様はもちろん、その周囲の環境を含めた安全性の確保を非常に大切に考えています。今後、新型モビリティに対してお気づきになったことがあれば、乗ったことがない方でもぜひお声をいただければと思いますし、我々としてもそういった情報を参考にしながら今後の事業展開を検討していきたいと考えています。