お客様の声
セコム医療システム株式会社
ソリューション本部 ホスピスネットセンター
センター長 柳澤 博行 様
ソリューション本部 ホスピネットセンター
常勤医 松村 美樹子 様
医療現場の放射線診断専門医不足解消に挑む
──TMJに委託されている遠隔画像診断支援サービス「ホスピネット」のコールセンター業務についてお話を伺う前に、同サービスについてご紹介いただけますでしょうか。

ソリューション本部 ホスピスネットセンター
センター長 柳澤 博行 様
柳澤様 ホスピネットは、1994年にスタートした日本初の商用遠隔画像診断支援サービスです。サービス開始の背景には、画像診断(読影)ができる医師の不足があります。サービス開始時の人口を見ると、中国が13億人、アメリカが3億2,000万人、日本が1億2,700万人で、日本の人口は中国の10分の1、アメリカの3分の1ですが、国ごとの検査装置の保有台数には大きな違いがありません。つまり、日本は検査装置が多い検査大国なのです。
加えて、検査装置の進化により1件あたりの検査時間が短縮されたことで検査件数が増加しています。CT画像も100枚から200枚、300枚と撮影枚数が増えたことで、読影に時間がかかるようになりました。以前は拍動しているため、撮影が難しかった心臓の画像がかなり鮮明に撮影できるようにもなりましたが、こういった分野は日が浅いために読影できる放射線診断専門医(以下、読影医)が十分におりません。
読影医でなくても医師免許を持っていれば画像診断はできますが、日本は圧倒的に医師の数が少なく、読影医となるとさらに少ないです。読影のプロが少ないという現状は、今も変わっていません。
現在、ホスピネットを契約している医療機関は約370施設、読影医の登録者数は約150人に及びます。
──読影医不足の解消を目指すホスピネットのコールセンターで、TMJはどのような業務を担っているのでしょうか。
柳澤様 医療機関と読影医をつなぐ業務をお願いしています。医療機関から寄せられる依頼を、内容に応じて適切な読影医に振り分けていくので、差配業務と呼んでいます。
このほか、医療機関へ提出した読影レポートに関する質問や相談の受け付けと回答のフィードバックと、ホスピネットの利用に必要な端末の障害対応もお願いしています。
差配担当者の頭の中にある情報をスコア化する
──委託を検討した背景には、どのような課題があったのでしょうか。
柳澤様 コールセンターの受付時間は朝8時から夜9時までと長く、その間、応対できるオペレータが常駐していなくてはなりません。委託前は、派遣会社やハローワークを通じて人材を集めたこともありましたが、希望通りの人材が集まらなかったり、シフトに抜けができたりと、非常に苦労していました。
──差配業務が属人化していたという課題もあったそうですね。
柳澤様 はい。診療科が細かく分かれているのと同様に、読影医にも得意分野がありますから、差配をする際には考慮する必要があります。その他にも、差配する際にさまざまな検討項目がありまして、そのひとつが「レポートの書き方」です。
読影医の出身大学によって読影レポートの書き方に違いがあって、例えば、シンプルに重要事項にフォーカスして書くことをよしとする医師と、しっかり丁寧に長く書くことをよしとする医師がいます。
一方、医療機関側にも同様に好みがあります。医療機関の好みの読影レポートを提出できるようマッチングさせるのですが、医療機関、検査内容、読影医の相性がオペレータの頭の中に記憶されており、差配が属人的になっていました。
この状況を知ったTMJから、オペレータの頭の中にある情報をスコア化して、差配をアシストする機能をオペレーション支援システムに搭載することを提案していただき、開発に取り組みました。これまでは、その必要性を認識していたものの、通常業務をこなしながらでは着手することができなかったことです。業務委託により担当者に時間の余裕ができたことが大きかったと認識しています。
ホスピネットの利用に必要な端末の障害対応においても支援システムを使っているので、こういうふうに使いたいとか、こんなふうに情報共有できたらいいとか、お互いに意見を出し合いながら開発を進めていきました。
経験値の違いによる品質のブレを業務の標準化で解消
──業務の運用状況をどのように見ていらっしゃいますか。

柳澤様 立ち上げ直後は改善や整備すべきことなどで苦労もしましたが、業務が走り始めてからは改善策を考えながら動いてくれていますし、何より人員の確保や配置に悩むことがなくなり、非常に助かっています。
ホスピネットには、検査画像を受け付けてから1時間以内に読影レポートを返却する緊急読影のオプションサービスがあります。これがとても人気で、1日に300件ほど寄せられていまして、緊急読影ができるからとホスピネットを契約してくださっている医療機関もあるほどです。
しかし、1時間以内のレポート返却を実現し続けるのはかなり大変です。検査画像が送られてきてからオペレータが登録作業を行って読影医に配信するまでに10~15分を要するため、読影医は45分ほどで画像を読みレポートを書き上げなければなりません。どの読影医が何件受け持っているか、終わるまでにどのくらいの時間を要するかを予測しながら、レポートが早く完成しそうなところへ差配しており、緊急読影のサービス品質の維持はTMJの差配によるところが大きいと感じています。
また、モニタリングを実施しているのですが、そのスコアが我々の学びや気づきになることも多くあります。先ほどお話しした差配アシストのシステム化は、業務経験の長短にかかわらず誰でもできるように標準化する必要性に気づけたから実現できました。いつまでも職人技なんて言っていてはだめだと思います。私がいなくても、誰かがいなくても、業務が回る状態を作ることも仕事なのだと考えられるようになりました。
読影医を支える“ただの業務連絡ではない”コミュニケーション
──非常に嬉しいお言葉をいただき、ありがとうございます。
松村様は読影医としてオペレータとやりとりをされています。オペレータからの確認や相談内容について、どのような印象をお持ちでしょうか?

ソリューション本部 ホスピネットセンター
常勤医 松村 美樹子 様
松村様 直接、医療機関とやり取りする必要のないことが精神的負担の軽減になっています。私は他の読影医が書いたレポートへの相談対応を依頼されることが多いのですが、伝え難いことも間にオペレータが入ることで角を立てずに伝えることができ、大変助かっています。
また、柳澤も話していましたが、読影医にはそれぞれ得意分野があるので、それを把握した上で検査依頼を配信してもらえるのは大変ありがたいです。
私は常勤医なので、夜間や日曜日には1人で対応することがあります。緊急時には得意分野外の読影にも対応しなければいけないのですが、検査依頼を配信するオペレータが「今は他に対応できる方がいないのですみません」と気遣いの言葉を添えてくれると、こちらの特性を把握してくださっていてありがたいという気持ちになります。当番が終わるときは、「お疲れさまでした」と声をかけてくださるので、面識はありませんが、ただの業務連絡ではないコミュニケーションが取れているように感じます。体調を崩した日の翌日に勤務開始の連絡をした際には、「体調は大丈夫でしょうか」と気遣っていただけたことも嬉しかったです。
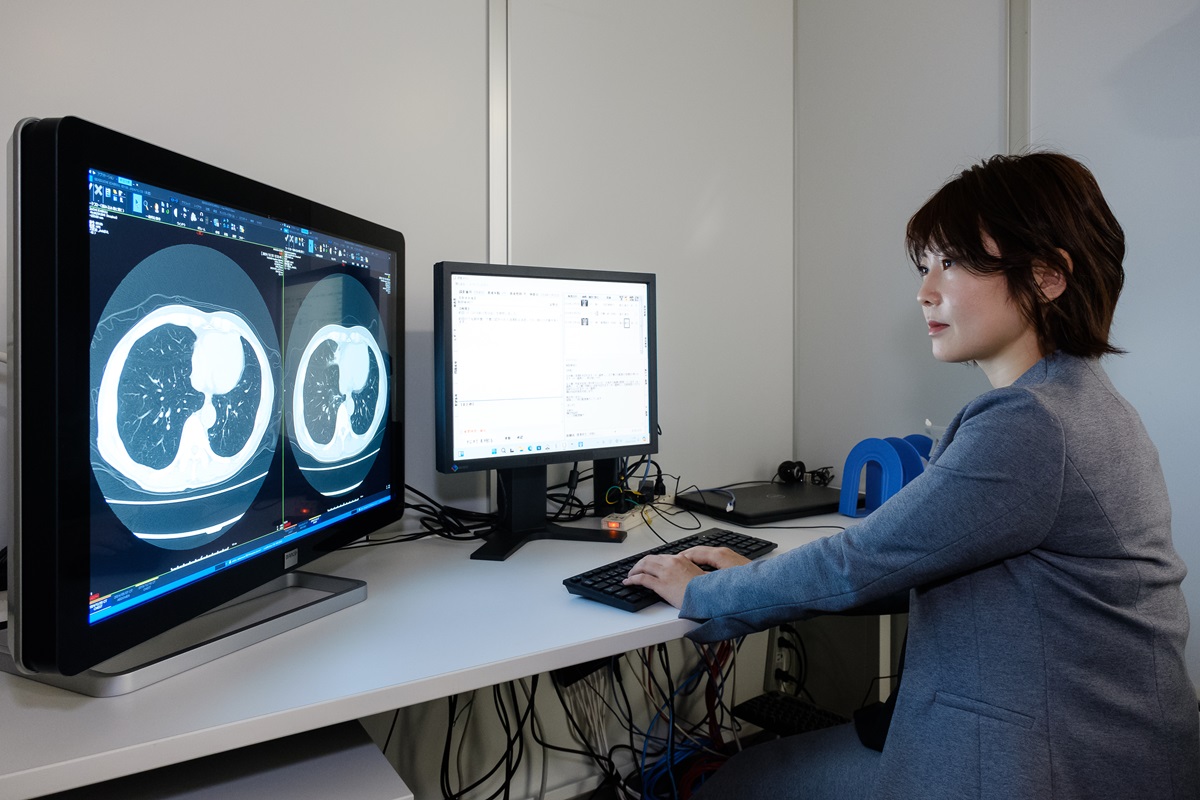
──たくさんのエピソードをご紹介くださり、ありがとうございます。TMJでは、業務内容に合わせて必要な適性能力を見極め、人材の採用を行っております。日々のやり取りが、読影医の皆様にとって心地よいと感じていただけているようでしたら、大変光栄に思います。
世界中どこにいても格差のない医療を提供するために
──柳澤様にお伺いします。委託開始の前後で感じた変化や効果はありますでしょうか。
柳澤様 現在、東京と関西の2拠点で業務を行っているため、システムの冗長化という意味でも効果が生まれています。台風でオペレータが出勤できないから東京で受け付けるとか、その逆もしかりです。
──委託業務および関連業務における今後の展望をお聞かせください。

柳澤様 さらなるBCP対応として、在宅勤務を可能にしようとトライアルを始めました。将来的に、非常時は在宅で縮退運転ができるようにしたいと考えています。
大きな視点での展望で言いますと、世界中どこにいても格差のない医療を提供できるようにすることを事業理念としており、その一端を画像診断で担っていきたいという志を持っています。世界各国からデータを受け取り、世界規模で読影医を束ねて画像診断を提供していきたいです。生体情報や年齢、性別といった個人情報の取り扱い、国による医師免許の違いなど、クリアしなければならない問題はいろいろあるのですが、実現させたいですね。
──日本の読影医不足の解消から、世界への市場拡大まで、共に歩んでいくことができますと幸いと存じます。本日はありがとうございました。



