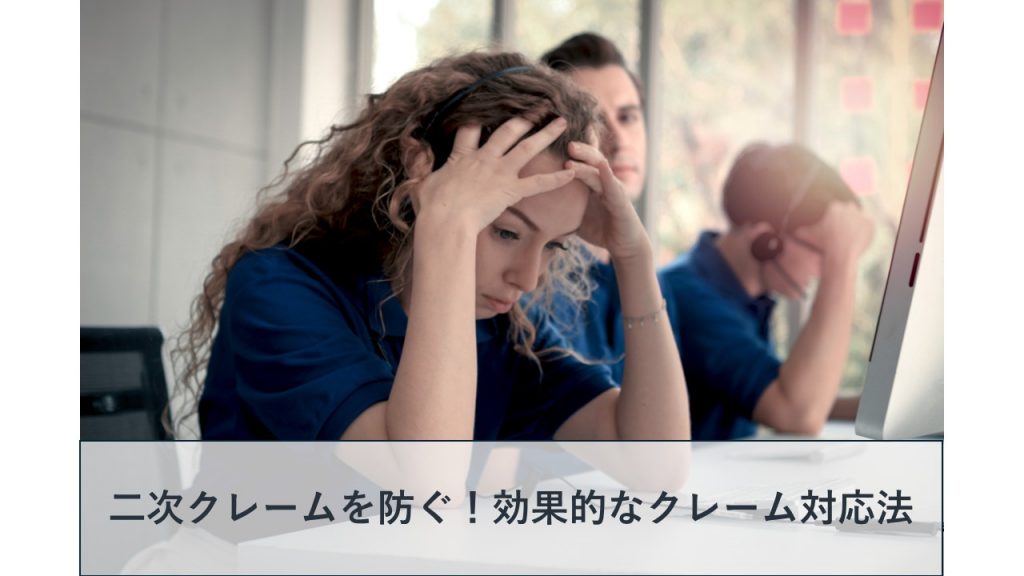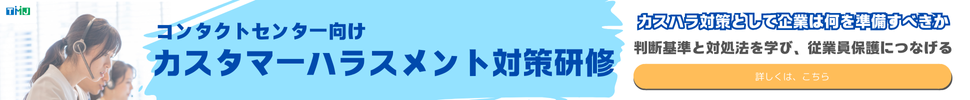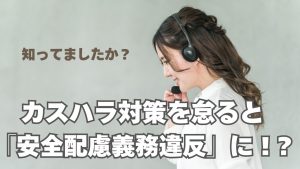品質向上
「クレームは宝の山」とも言われるように、企業にとって改善の機会を得るための貴重な情報です。そのため、企業はクレームをネガティブなものと捉えず、顧客との関係を強化するための重要なステップとして考えることが大切です。
一方で、「長時間の対応を強いられる」「理不尽なことを言われ続ける」「暴言を吐かれる」等、お客様の行き過ぎた言動が社会的に問題視されており、お客様を正しく尊重することや適切なクレーム対応で、二次クレーム、さらにはカスタマーハラスメントへと発展させないことも企業に求められるようになってきました。
このコラムは、改めて企業として正しいクレーム応対ができているかどうかを確認するきっかけとしていただければ幸いです。
クレームの意味と背景
そもそも「クレーム」とは、何でしょうか。
クレームは、英語で「権利を主張する・要求する」の意ですが、応対の中では、お客様の「不満、苦情」も含んだ「商品・サービスに対するお客様の不満の具体的な表現」だと言えます。
クレームが生まれる背景には、お客様が商品・サービスを受けた際の期待値と実態のギャップがあります。
そこには、お客様の真のニーズが隠されている場合があるため、クレームは自社の商品・サービスの改善に繋がる貴重な情報が含まれていると言えます。
また、クレームをいただいたお客様に対して、適切な応対ができれば、お客様は商品・サービスのリピーターとなってくれることは少なくありません。企業はクレームをネガティブなものと考えず、顧客との関係を強化するための重要なステップとして捉えることが大切です。
クレームとカスハラの違いとは?
昨今、カスタマーハラスメント(通称カスハラ)は、従業員保護の観点で、社会的な課題としてニュースに取り上げられることが多いですが、お客様からの正当なクレームを安易に「カスハラ」と決めつけて誤った対応をすることは、絶対に避けなければなりません。
カスタマーハラスメントに対する正しい理解をしないまま「暴言を吐かれた。カスハラだ」と安易に決めつけるのは危険です。
お客様の不満の内容をしっかりと把握することで、それは正当なクレームなのか、不当なクレームなのか、カスハラなのかを見極めながら応対することが望まれます。
改めて、クレームとカスタマーハラスメントの違いについて確認していきましょう。
クレーム
自社の商品やサービスに対する不満を持たれたお客様の具体的な表現を指し、不満や苦情、消費者として当然の権利の主張・要求が含まれます。例えば、商品やサービスに過失があった場合、それを消費者の権利として主張・要求することは正当なクレームと言えます。
しかし、主張の仕方に脅迫や人格否定、差別的言動などが含まれていたり、要求が社会通念に照らしてふさわしくない場合は不当なクレームとなります。
カスタマーハラスメント
クレームの一次応対の重要性
クレーム応対の基本的なステップの説明の前に、クレームの一次応対の重要性については、理解しておいてください。クレームには、商品・サービス・起こった出来事に対する一次クレームと、クレームを伝えた際の企業の対応や言動に対する二次クレームがあります。一次クレームで適切な応対ができていないと、その応対の中で新たな不満が生じ、二次クレームに発展することがあります。クレームの火種が大きくなってから収束に向かうには、かなりの労力が必要となり、精神的な疲労も増してしまいます。クレーム応対においては、通常の応対よりも丁寧に、より迅速に、そしてより正確な応対を心掛けていきましょう。
クレーム応対の基本的なステップ - 問題解決への道筋
クレーム応対は、顧客の信頼を取り戻すために正しいステップを踏んでいく必要があります。
以下にそのプロセスを詳しく説明します。
STEP1 受け止め
お客様の声や言動が感情的だと思ったら、冷静なお話ができるまで、ひたすらお客様のお話に耳を傾け、お客様の気持ちを受け止めることが大切です。
「この人は自分の話を分かってくれている」「この人なら任せられる」と思っていただけるようになったら、その後のステップがスムーズに進められます。
人の怒りは30分しか持続しないといわれています。
まずは、お客様のお話に耳を傾け、お客様の気持ちを受け止めて、信頼関係を構築することが大切です。
STEP2 状況把握
次にお客様が何に対して不満を抱いているのか、その心情を正しく把握する必要があります。例えば、謝罪を求めているのか、問題解決を希望しているのか、損をしたくないのかなどです。ここを正確に把握できていないと、要望に合った提案や説明ができず、お客様の怒りが再発してしまう可能性があります。また、的確に把握することは、「不当な要求ではないか?言いがかりではないか?」など、カスタマーハラスメントの判断基準でもある「要求内容に妥当性があるか」の検討にもつながります。相手の話の中には推測や意見も含まれているため、客観的事実を掴むことが重要です。
STEP3 提案・説明
クレームにつながった相手の問題に対して、どのような解決ができるのか、代替案や解決策の提案を行うフェーズです。曖昧な表現は誤解を招き、専門用語ばかりの説明は言い負かそうとしているように聞こえることがあります。端的でわかりやすい言葉で説明するように心がけましょう。状況によっては「できないことはできない」と丁寧に説明する必要がある場面もあります。提案・説明にはわかりやすさと感じの良さを意識し、顧客の不満解消と企業の信頼性向上につなげたいところです。
STEP4 クロージング
クレーム応対の中では、お客様の要望通りの提案ができないこともありますが、貴重なご意見をいただけたことに対する感謝の気持ちを伝え、これからも関係を続けていきたいという意思を示すことは大切です。クレーム処理と再購入決定率の間に相関関係があるとされる「グッドマンの法則」では、お客様の82%がリピーターとして、その会社のサービスや商品を再購入してくれるという分析結果があります。改めてクレーム応対の重要性を確認し、最後まで丁寧に対応しましょう。
クレーム応対のその後- お客様の声を生かす履歴記録の流れ
クレームが1件ある場合、同様の不満を抱えている方が潜在的に26人いると言われています(「グッドマンの法則」)。
応対後に、この1件のクレームを分析し、共有することには次のメリットがあります。
・応対マニュアルの見直しなどで同様のクレーム再発防止や対応時間の抑制ができる
・商品・サービスの改善のきっかけとなり企業成長が見込める
・リピーターになってもらい顧客の流出を防げる
以上のように、企業はクレームを成長の機会と捉え、積極的に活用していくことが求められます。
TMJでは、クレーム対応の基礎~応用を学べる研修サービスを提供しております。
お客様の現状課題と期待効果、受講者層、人数、実施時間、開催形態を伺った上でご提案します。
ご興味のある方はお気軽にご相談ください。
キーワード
関連するサービス |
|---|