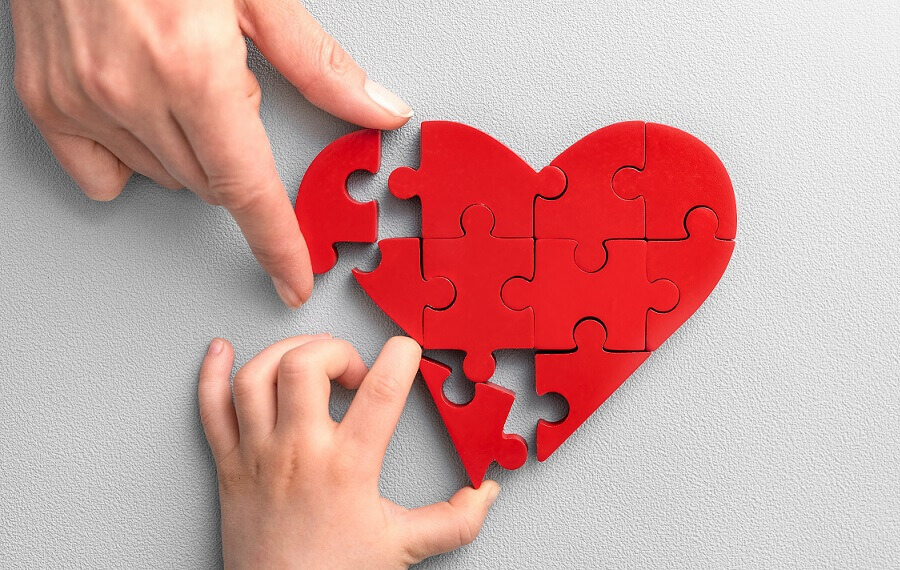現場カイゼン
新型コロナウイルスの感染拡大で、初めてのこと尽くしで対応に追われている方も多いのではないでしょうか。前例がない状況の中で、対応を求められているのはコールセンターも例外ではありません。
本記事では、株式会社TMJのコールセンターの現場にスポットを当て、「コロナ禍におけるオペレーターのモチベーションアップ施策」をテーマに現場での取り組みについてご紹介します。今回は、全5回の連載の第3回目となります!
第3回は、保険会社のコールセンターでアカウントマネージャーを務める大宮路AMとセンター現場でSV(スーパーバイザー)を務める土井SVにお話をお伺いしました。お客様から保険に関する様々な電話でのお問い合わせに、コールセンター勤務と在宅勤務の2つのチームの総勢約20名で対応する現場でのお取り組みについてお二人にお話を伺いました。
コロナ禍で、在宅勤務とセンター勤務の2チームに分かれての運営
Q:新型コロナウイルスの感染拡大が進む中で、現場の状況はいかがでしたか。
大宮路AM: 4月初旬に、人数を限定した上で部分的に在宅オペレーションを取り入れることが決まりました。在宅オペレーションを実施する上での人選、ルール決め、対応品の準備、事務手続きなど必要な対応が全て初めての中で、手探りで在宅オペレーションに向けて準備を進めていきました。
土井SV:在宅オペレーションを取り入れるという初めての任務に対して、とにかく目の前のことをやっていこうと精いっぱいでした。
Q:在宅オペレーションを取り入れられる人数が限定されている中で、どのように人選を行ったのでしょうか。
土井SV:在宅勤務ではセンターと異なり、管理者にすぐにエスカレーション(※)できる環境ではないため、経験値が高い方を優先的に選びました。在宅勤務希望者が多くなるのではと想定していたのですが、意外と在宅で仕事をすることへの不安感の方が強く、センターでの勤務を希望する方が多かったです。
※エスカレーション:顧客応対時に、オペレーターが自身だけでは対応が難しく、質問や確認をしたい際に、管理者の指示を仰ぐこと。
在宅オペレーションで直面した「オペレーターの孤独感」解消への取り組み
Q:そんなイレギュラーな環境の中で、オペレーターの方々のモチベーションに変化はありましたか。
土井SV:特に最初の頃はPC障害をはじめとする機械トラブルでセンター時と同じように顧客応対を行えない時があったり、エスカレーションですぐに相談できないもどかしさがあったりと不安が大きいという声がありました。在宅勤務のオペレーターの方々の孤独感をいかに解消するかが大きな課題でした。
Q:コロナ禍の在宅勤務という環境で、オペレーターの方々が孤独感を感じていることを知った中で、どんなことに注力していたのでしょうか。
土井SV: 大きな不安材料になっていた機械トラブルに関しては、先に在宅勤務を始めていた他のユニット(チーム)の管理者から情報を収集し、大きく改善しました。
また、チャットや電話を活用し、オペレーターが困っている時に管理者がすぐに気付けるように工夫をしたり、音声によるリアルモニタリングを在宅環境でも実施したりと、センターに可能な限り近い環境を作ることで、孤独感が少しでも解消できたらと取り組んでいました。
Q:在宅勤務のオペレーターの方々も2週間に1回程度センターへ出勤するという取り組みも行われたと伺ったのですが、いかがでしょうか。
土井SV:在宅勤務の方が一人で悩みを抱え込まないように、2週間に1回程度センターへの出勤の場を設けることで、実際に会って在宅勤務での困りごとや様子についてヒアリングを行っていました。
Q:在宅勤務のオペレーターの方々が思うように業務に取り組めない環境もあった中、センターで勤務をするオペレーターの方々の状況はいかがでしたか。
土井SV:センターでは管理者がすぐ近くにいてエスカレーションできる環境があったため、難易度の高いお問い合わせは全てセンターで対応する形を取っていました。また、在宅勤務で機械トラブルが多かった時期はセンターのオペレーターが対応し、フォローする体制だったため、センターのオペレーターに負担がかかっていた部分がありました。
そのため、在宅勤務とセンター勤務のオペレーターの間で、溝が生まれてしまったり、センター勤務の方のモチベーションが落ちてしまったりしないか心配でした。
そこで、週に1回在宅受電の状況を伝えるメルマガを配信し、在宅勤務の状況や苦労の部分をユニット全体に向けて伝えていきました。情報を発信していくことでお互いの状況の理解が深まり、在宅勤務の方がセンターに来ると、センター勤務の方とお互いを励まし合う姿も見られて少し安心しました。
日頃のコミュニケーションの土台があったからこそ発揮されたチームワーク
Q:これまでの取り組みを通して、オペレーターの方々のモチベーションに変化は見られましたか。
土井SV:オペレーターの方々に、全てのことが初めてだから一緒に頑張っていきましょうねと話したら、「頑張ります、TMJが在宅でオペレーションをやったという歴史を残します!」と言ってくれる方もいらっしゃったり、他にも声をかけてくださる方も多かったりで、少しずつオペレーターの方々の孤独感も和らぎ、モチベーションも回復してきているのではと感じました。
大宮路AM:ここのセンターは離職率が低く、長期雇用を実現できていた部分があり、コロナ禍前からチームとしての仲間意識が強かったかもしれません。少人数で難易度の高い業務を行う上で、SVとオペレーターがチームを組んで取り組んでおり、面談やフィードバックなどのベースのコミュニケーションを大切にしてきました。今回の新型コロナウイルスの感染拡大という大きな変化があってもお互いが協力しあう文化ができていたからこそ、歯車が崩れずに業務を進めることができたのではと感じています。
また、現場を取りまとめる土井さんを支えたいという文化も実はあるのです。土井さんが現場を取りまとめる立場になったのも4月からで、初めてのこと尽くしの中で新型コロナウイルスが流行し、在宅オペレーションを導入するという状況で、土井さんが奮闘する姿を現場の人たちは一番近くで見ていました。
土井SV:私自身そういった励ましの声があったからこそここまでやってこられたと思います。まだ道半ばで、孤独感が完全に解消されたわけではないので、これからも改善を重ねていきたいと思います!
編集後記
コロナ禍前から地道に重ねてきた日頃の取り組みが、新型コロナウイルスの感染拡大という象徴的な出来事があっても、現場に大きな混乱を招かずにチームワークを発揮する土台となったのではと思います。その場限りではない現場の方々全員で作り上げて生まれた結束力に、大きな底力を感じました!(業務改善ノート編集部:安田(恵))
株式会社TMJでは、コールセンターサービスを軸に、クライアントの課題に合わせたカスタマーケアサービスを提供しております。また、業務の可視化を可能とする業務量調査・分析パッケージも提供しています。ご検討の際は、ぜひご相談ください。お問い合わせは、<こちら>。
※株式会社TMJではクライアントと協議の上、一部で在宅勤務を実施しております。
キーワード
関連するサービス |
|---|