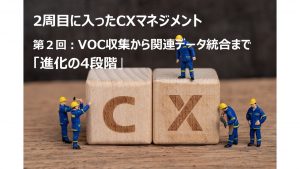専門家コラム
多くの企業で実践されている「CX(顧客体験)向上の戦略」について、全6回の連載形式で推進方法を解説しています。最終回である6回目では、ボトムアップの流れとは逆に、中期経営計画としてトップダウンでCX・DXを推進する国内生命保険会社の事例から、事業計画をいかに顧客接点の具体的な活動に落とし込み、かつ形骸化させず成果を創出するのか考えます。
国内生保会社におけるDX強化の波
国内大手生命保険会社のA社では、全社中期経営計画の中核にDX強化による事業変革、サービス変革を据えています。A社に限らず、とくに国内生保会社においては、強固な対面営業基盤をさらに有効活用するため、多様化する顧客ニーズに対し、デジタル化によるコミュニケーションの利便性向上や、AIなど先端技術を活用した業務変革(事務プロセスの効率化)に注力しています。
A社では、こうした取り組みのためDX推進のための予算を計上。各部門に配分し、部門単位でDX強化を推し進めています。
大方針「DX強化」に向けて

では、かねてより運営上の課題解決の一環としてCX向上に取り組んできた国内大手生命保険会社のA社のコンタクトセンターが、「DX強化」という大方針を受けて実際にどのような取り組みを行ったのかをみていきましょう。
大方針を現場に落とし込む
A社のコンタクトセンターではまず、DX強化という全社の大方針を受けて、FAQサイト、AIチャットボット、有人チャット、問い合わせフォームといったWebを起点とする顧客接点のデジタル化を推進しました。対面営業が難しいコロナ禍において、コンタクトセンターやWeb上のサポート、マイページ(契約者専用ページ)の重要性が増しており、デジタル化はCX向上の観点でも急務でした。
一方、応対支援・データ分析には、音声認識システム、テキストマイニングツール、内部ナレッジシステムを導入しました。
シンプルで数値化できる目標設定
上記の取り組みを踏まえ、A社は以下の目標を掲げることにしました。
- 無人サポートの導入による問い合わせの削減
- 有人サポートのマルチチャネル化による電話比率の低減
- 応対支援ツールの導入による応対生産性と品質の向上
- 音声認識ツールの導入によるVOC活用
目標設定においては、経営層に対し全社中期経営計画の目的に沿った成果をわかりやすく伝えられることと、DX・CX向上で目指すものを部門内に浸透させやすいことを考慮し、シンプルかつ数値化できるものを中心としました。これは、第5回でも触れた「共通言語化」と同じ観点です。
失敗を経てデジタル化を成功させるために
A社のデジタル化以前のコンタクトセンターは、電話応対が大部分を占め、応対の生産性や品質は個々のオペレータのスキルに依存していました。そのため、契約数の増加に伴うコール増への対応で手いっぱいという状況でした。
こうした中で短期間にデジタル化を推進した結果、ノウハウやリソースの不足により、成果創出が停滞する事態に陥っていました。これはA社に限らず、トップダウンでDX・CXを推進する企業の多くが直面する課題といえます。そのような状況に対してTMJが提案・実施した対応は以下のようなものでした。
現状把握から施策の立案
問い合わせを削減するという目的に対し、まずは現状を把握。その後、「件数の多いもの」「Webでの自己解決のしやすさ」「お客様視点での自己解決ニーズ」の3つを切り口に、削減すべき問い合わせカテゴリを選定しました。
そのうえで、音声認識によりテキスト化された応対履歴をテキストマイニングツールで分析し、問い合わせ内容の詳細と件数を定量的に把握。FAQやチャットボットのコンテンツの有無、Webサイトの検索・閲覧の状況から、対策を具体化していきました。
行動計画の作成
続いて、対策実行のための活動計画を作成しました。とくにマルチチャネル化やセルフサポートに関しては、部門間連携が必須になります。A社の場合は、Webやシステム部門に、データやVOCなどを根拠に地道に協力を呼びかけ、巻き込んでいきました。
加えて、成果創出の停滞要因であったノウハウやリソースの不足に対しては、TMJ本社の支援部門が担うことを提案。その中には、段階的にA社の社員が自立自走で目標を達成できるように支援する計画も加えました(図)。
取り組みの成果
A社の改善活動は現在も進行中ではありますが、すでにいくつかの成果を創出することができています。
- FAQ閲覧数が約2倍に増加
- チャットボットの利用数が約4倍に増加
- 削減対象とした問い合わせカテゴリにおける問い合わせ数削減
上記の成果に加えて、A社では改善活動や数値分析などの運用が定着。TMJからA社社員へのノウハウ移管も順調に進んでいます。
全6回を振り返り

CX戦略の実践においては、各社それぞれに課題を抱えていることでしょう。そういったときは、ぜひCX推進2周目の要素を軸に社内の取り組みを点検し、CXをリ・デザインしてみてはいかがでしょうか。そして、本連載で提言してきた課題への対応策が、貴社のCX戦略を推進するうえで一助となれば幸いです。TMJではCX向上に関するご相談も受け付けております。詳しくは<こちら>。
キーワード
関連するサービス |
|---|