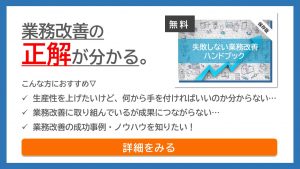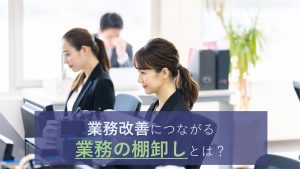BPOの基礎知識
「業務の見える化」は、業務改善や生産性の向上に有効な取り組みです。業務を見える化することで業務プロセスに潜む課題を適切に把握でき、課題解決のための最適な改善施策の立案が可能になります。業務の見える化は、安定して利益を上げ続けられる企業体制を築くことにも役立つため、取り組みを強化する企業が増えています。今回は、業務の見える化とは何か、取り組むことのメリットや進め方、実際に取り組みを行った企業の事例をご紹介します。
業務の見える化とは

業務の見える化とは、組織内の業務の内容を明らかにし、担当以外でも業務の状況を把握できる状態にすることで、「業務の属人化をなくし、誰でも取り組めるようにすること」を指します。
業務の見える化ができていないと、担当者にしか業務状況がわからず、担当不在の場合、最悪、業務がストップしてしまうといった危険があります。業務の見える化を進めることで、業務がブラックボックスになることがなくなり、あわせて業務を標準化することで、業務品質の均一化にもつながります。
なぜ、業務の見える化が注目されているのか
業務の見える化で、業務改善による生産性の向上と属人化の阻止が可能となり、限られた労働力でも企業として利益を出し続けることができるようになります。
もし、業務が属人化し、担当者への業務負荷が増大すると、長時間労働などのさまざまな弊害が生じる可能性があります。また、今後予想されている労働力人口の減少への備えの面でも、労働生産性を高めることは重要です。
業務の見える化のメリット
業務の見える化による3つのメリットを紹介します。
① 業務効率化と生産性向上が期待できる

業務の見える化は、実施業務を全て洗い出すことから始まります。業務全体を把握することで、これまでは見えていなかった重複業務や不要業務が明確となり、業務フローをシンプルにすることで業務の効率化と生産性の向上を実現できる可能性があります。
また、従業員一人ひとりの業務の見える化を行うことで、特定の従業員に業務の負担が偏っていないか、業務量の可視化も可能となります。
業務の見える化を通して、改めて業務全体を見直し、改善すべき業務やフローを特定し、業務改善への取り組みを強化しましょう。
② 部署間の連携が取りやすくなる
業務の見える化を行うことで、「誰がどのような業務を行っているか」を把握できるようになります。業務内容や役割が明確になることで相互理解が進み、部門同士の連携が取りやすくなります。
業務の見える化の際には、業務内容をマニュアルとして残し、定期的にアップデートすることが重要です。
言葉では説明が難しい業務であっても、フローチャートや表など視覚的な要素を資料に盛り込むことで、業務内容の理解促進につなげることができます。
また、マニュアルとして残すことで業務内容の認識のズレを防ぐことができ、他部署へ協力を依頼したい場合にもスムーズにコミュニケーションを取ることができます。
業務の見える化を進めることで、部署間のスムーズな連携と、効率のよい業務推進を実現しましょう。
③ 人事評価がしやすくなる

業務の見える化によって、「誰が、いつ、何をしているか」を評価者が正しく把握でき、人事評価がしやすくなります。
業務が属人化した組織では、人事評価の判断基準がわかりづらくなりがちです。業務の見える化に取り組むことで、各担当者の業務内容を把握し、成果を評価しやすくなります。また、評価の説明にも具体性が増し、担当者のモチベーションを高められる可能性もあります。公明正大な人事評価を行うためにも、業務の見える化は重要といえます。
業務の見える化の進め方
業務の見える化に取り組む際の進め方について解説します。
① 業務の抽出と業務量調査

業務の見える化は、まずどのような業務があるのかの洗い出しから行います。
次に、洗い出した業務それぞれについて、どの程度の工数がかかっているのか、担当部門への調査を行います。
これらは、インタビュー、アンケート調査、現場のモニタリングなど様々な方法で行うことができますので、自社の環境に適した方法を選択するとよいでしょう。
② 業務分析

調査結果をもとに、業務分析を行います。業務の難易度や業務の負荷、属人化などの視点も含めて分析することが重要です。
③ 業務フローの作成と課題の抽出

業務分析で問題があると仮定した業務について、業務のフローを作成します。担当者への負荷低減、客観性の担保、課題抽出の際の気づきなどから、業務の担当者へのヒアリングなどを通じて作成するケースも多いです。
作成した業務フローから、業務プロセスの中に潜む問題やその原因、ボトルネック、他部門との連携上の課題などを明らかにします。問題・課題を一覧表などにして整理するとよいでしょう。
④ 業務改善計画の立案
業務改善施策を検討し、改善計画を立案します。実現可能性や費用対効果、本質的な改善策かなどをふまえることが必要です。
⑤ 業務改善施策の実行
立案した業務改善計画に沿って、改善施策を実行します。改善した業務について業務マニュアルを作成し、社内に展開することもポイントです。
一定の業務遂行を行った段階で、改善効果の検証を行うことが不可欠です。改善施策は計画通り行われているか、どの程度効果があったのかを把握し、改善のPDCAを回し続けることが必要です。
成功事例「専門商社のシェアードサービスセンター」を紹介
 グループの間接業務を受託するシェアード会社として設立。管理部門間で重複している業務を集約するために、現状把握に着手しましたが全体把握が難しい状況にありました。さらに、部門間の共通言語がなく、社内のやりとりのしにくさも指摘されていました。
グループの間接業務を受託するシェアード会社として設立。管理部門間で重複している業務を集約するために、現状把握に着手しましたが全体把握が難しい状況にありました。さらに、部門間の共通言語がなく、社内のやりとりのしにくさも指摘されていました。
そこで、導入したのが株式会社TMJの「業務量調査・分析サービス」。テンプレートをもとにヒアリング・業務の棚卸を実施した結果、定型業務や単純業務に費やす時間が全体の約8割を占めていることが判明。社員全員が同じデータを見て意思疎通がとれるようになったことで、業務フローの見直しが順調に進んでいます。
業務の見える化で企業の生産性を高めるために

業務の見える化を行うことで、担当者に依存することなく業務を遂行でき、業務の属人化を防ぐことができます。同時に、業務品質を保ちながら、企業の生産性を高めることができます。
また、従業員にとっても「自分がいないと業務が回らない」という心理的な負担が軽減されます。
株式会社TMJでは、業務の見える化に活用いただける業務量調査・分析パッケージサービスをはじめ、企業の生産性向上に貢献できる幅広いサービスを提供しております。業務の見える化をご検討の際は、ぜひご相談ください!お問い合わせは、<こちら>。
キーワード
関連するサービス |
|---|