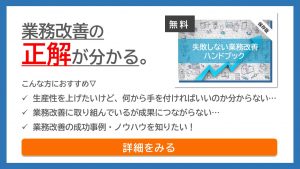BPOの基礎知識
受発注業務は業務範囲が幅広く、業務効率化に課題を抱えている企業も少なくありません。業務を見直し、最適な方法を取り入れることで業務効率を向上させることができます。今回は、受発注業務の効率化を阻む課題や効率化を実現する4つの方法を解説します。
受発注業務とは
受発注業務とは、一般的にお客様から注文を受けてから商品やサービスを実際に届けられるまでの一連の業務を指します。
- 金融商品の売買
- テレビショッピングやECなどの通信販売
- 製造業や卸売業をはじめとするBtoBビジネス
など幅広い業界で発生します。
今回の記事では、BtoB向けビジネスにおける受発注業務を中心に解説していきます。
まず顧客からの注文内容を元に見積りを作成し、内容に同意がとれたら発注処理を行います。商品や製品の在庫がない場合には、仕入れ元と連携し、確保します。そして、製品の準備が整い次第、顧客へ発送します。顧客は届いた製品の検品を行い、問題なければ請求書の内容に沿って支払いを行います。製品が納品されるまで、業務内容は多岐にわたります。
受発注業務を効率化する上での課題
受発注業務を効率化する上でどんな課題があるのでしょうか。ここでは、受注業務を効率化する上での課題について解説します。
関係者間の連携不足
受発注業務は、複数の部署が連携することで成り立っており、連携する上で必要な業務量が膨大で、効率的ではなくなっているケースがあります。また、業務の進捗状況が可視化されていないことで、想定以上にコミュニケーションコストがかかっていることもあります。
受発注業務において正確さは非常に大切で、顧客が注文した商品やサービスを指定された日時に届ける必要があります。受注業務での正確さは企業全体の信頼にもつながるため、常に慎重に業務を進める必要があります。
営業担当者だけでなく、在庫管理部門、経理部門、販売管理部門など様々な関係者が受発注業務にたずさわっており、連携の取りやすさが効率化を進める上で非常に重要です。
業務フローの属人化
業務フローが属人化してしまい、担当者によって進め方が異なり業務が非効率になる可能性があります。
たとえば、業務を進める上で発生する確認・調整・判断の進め方が担当者によって異なり、業務効率化を妨げているケースがあるのです。
また、業務フローが属人化されていることで、業務マニュアルと現場で実施されている業務フローが異なり、結果的に業務フローが整備されていないことがあります。
システム間の連携不足
受発注業務の効率化が進まない企業は、システム間の連携不足で人手に頼った業務が多くなっている傾向があります。
たとえば、データを照会しながらの入力作業や発注数量の置換など単純作業でありながらも正確性が必要な業務をシステムの機能を活用しきれず、従業員がエクセルを使って手入力で対応しているケースがあります。また、システムとシステムの間で発生する作業を従業員が対応しているケースもあります。
従業員が対応することで、入力漏れや入力ミスなどの人為的なミスが起こる可能性があり、確認作業にも多くの時間がかかってしまうこともあるのです。
受発注業務を効率化する4つの方法
受発注業務を効率化するためにはどんな方法があるのでしょうか。ここでは、4つの方法に絞って解説します。
業務の可視化による業務の見直し
受発注業務の効率化を行う上で、業務可視化を行い、業務内容や業務フローの見直しを行うことが大切です。
業務内容の見直しでは、ムダな業務の洗い出しを行い、廃止や統合できる業務はないか見ていきます。業務によっては、ムダな業務が多く、業務量がふくらんでいるケースがあります。
業務フローの見直しでは、従業員によって業務の進め方にバラつきはないか、業務フローが明確であるか、情報確認に多くの時間を必要としていないかなど非効率を生んでいる原因は何か見極めることがポイントです。
受発注システムの見直し
自社の課題に合わせて受発注システムを見直すことは、受発注業務を効率化するひとつの方法です。
受発注システムが現状の業務に合っていないために、人手に頼った業務が発生し、手間がかかる業務フローになっているケースがあります。
受発注システムを見直し、現状の業務に合わせて機能を活用したり、アップデートしたりすることで、今まで従業員が行っていた業務を簡略化したり、自動化できたりするケースもあり、人手に頼った業務フローから脱却し、業務効率を高めることができます。
デジタル技術の活用
人手に頼っていた業務にデジタル技術を活用することで、業務効率化を進めることができます。
デジタル技術を活用し、業務を自動化することで従業員の業務負担を軽減し、効率化することができます。
自動化のひとつとしてRPAの導入があります。RPAとは「Robotics Process Automation」の略称で、パソコンを使った定型業務の一部をロボットに任せ、業務を自動化することを指します。AIのように学習機能はないため、過去データに基づいた判断はできません。その一方で、標準化されたルールに従い、正確な業務を行うことを得意としています。
RPAは24時間体制での稼働が可能なため、営業時間外でも業務に対応することができます。また、ルールに沿って業務を実施するため人為的なミスを削減でき、正確性を高めることができます。
RPAが業務の一部を担うことで従業員の業務負担が減り、企業の利益に直結するコア業務に集中することができ、業務効率をさらに高めることができます。
アウトソーシングやBPOの活用
アウトソーシング・BPOを活用することで業務効率化を実現することができます。
アウトソーシングとは、業務の一部を外部に委託することを指します。アウトソーシングでは、業務の代行にとどまりますが、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)では業務の実施だけでなく、業務プロセス自体を見直しながら企業の課題解決に継続的に関わる特徴があります。
<関連記事>BPOとは?アウトソーシングとの違いやメリット・導入時のポイントを解説
アウトソーシングやBPO事業者は受発注業務を効率的に実施するためのノウハウを蓄積しており、業務の実施に必要な人材を採用したり、設備や備品を自社で準備したりする手間を省くことができます。そして、委託した業務を効率的に実施しながら、従業員はコア業務に集中することができるため、企業全体の業務効率を高め、生産性の向上にもつなげることができます。
受発注業務の効率化に取り組むメリット
受発注業務を効率化させることでどんなメリットがあるのでしょうか。ここでは2つのメリットをご紹介します。
受注業務がスピードアップ
業務効率化を通して、受注業務をスピーディーに行うことができます。業務の一部を自動化したり、システムを導入したりすることで、人手に頼る業務を減らし、業務スピードを上げることができます。また、人為的なミスをなくすことで、正確性の向上も期待できます。
コア業務に集中できる環境作り
効率化を通して、業務負担が軽減することで従業員はコア業務に集中しやすい環境が生まれます。
たとえば営業担当者の場合、受発注業務に充てていた時間を新規顧客の獲得に向けた活動に充てる時間を増やすことが出来ます。
今まで定型業務にかけていた時間をコア業務に充てられるため、企業の生産性を高めるための取り組みを強化することができます。
受発注業務を効率化して、生産性向上を

企業によって受発注業務の効率化を実現する方法は異なります。業務を見直し、最適な取り組みを実施することで、企業の生産性向上にもつなげることができます。
株式退社TMJは、業務の把握に活用できる業務量調査・分析パッケージや業務効率化を後押しするRPAサービスや文書電子化サービスなど企業の課題に合わせて幅広いサービスを提供しています。BPOデザインも可能で、企業の課題に合わせたご提案も可能となります。受発注業務をはじめ、業務の効率化に課題を感じている方は、ぜひご相談ください!お問い合わせは、<こちら>。
キーワード
関連するサービス |
|---|