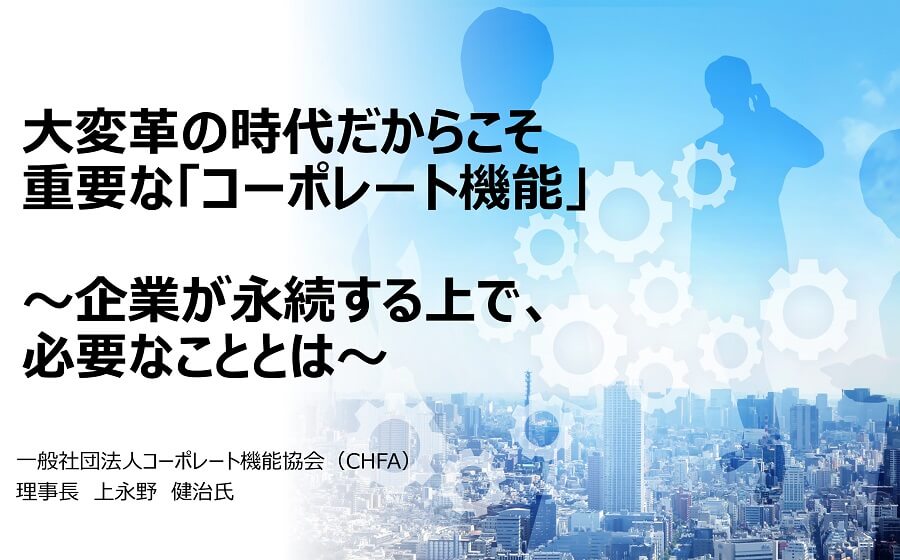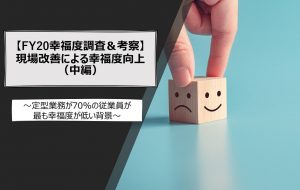専門家コラム
企業が継続し続ける上で、「コーポレート機能の強化」は見逃せないテーマとなっています。コーポレート機能は、財務・経理、人事・労務、法務、情報システム、総務などのコーポレートの各部門が担っています。
そんなコーポレート機能の業界団体・研究機関として、2020年4月に一般社団法人コーポレート機能協会(CHFA)が発足しました。公益法人等として、企業や自治体などのコーポレート機能に関する調査、研究、情報収集・提供、人材の育成・指導などの幅広い分野を通してコーポレート機能の革新に貢献し、日本企業や日本経済の発展に寄与することを目的として掲げています。
今回は、コーポレート機能協会の理事長を務める 上永野 健治 氏をお迎えし、お取り組みをはじめ、この変革の時代において企業が永続する上で必要なこととは何かお伺いしました。
【一般社団法人コーポレート機能協会 理事長 上永野 健治 氏】
経営者やマネジメント、ファイナンス、経理・人事、調達・総務、企業法務、国際・国内税務、さらにシェアードサービスをテーマとする研究交流活動に従事。2020年4月に一般社団法人 コーポレート機能協会を立ち上げ、企業・自治体・団体等のコーポレート機能の革新に向けて精力的に取り組まれている。
日本のコーポレート機能の革新に向けてのお取り組み
― コーポレート機能は企業にとって欠かせないものであり、近年、国内でもコーポレートガバナンス(企業統治)や機能強化が加速している印象があります。昨年、コーポレート機能協会を立ち上げたきっかけについて教えてください。
私はこれまでシェアードサービスに関する研究交流活動に長年携わってまいりました。コーポレート機能の研究の一環で以前、企画させていただいた海外視察(※1)にてニューヨークやロンドンを訪れた際に、「小さくて、強い」グローバル企業のコーポレート機能を目の当たりにしました。
世界規模で経済とビジネスが共に大変革する時代を迎える中、依然として日本は生産性やコーポレート・ガバナンスのあり方などについて海外から厳しい目で見られていると感じています。
日本のコーポレート機能の革新に少しでもお役に立ちたいと強く感じたことが立ち上げさせていただいたきっかけとなります。
― コーポレート機能協会ではどんな取り組みを行っているのでしょうか。
各種部会(研究交流会)の企画・運営をはじめ、リサーチコミッティ(研究委員会)による調査や研究活動などを行っています。
部会では、コーポレート機能に携わる異業種・同業種各社の方々にお集まりいただき、人脈形成や勉強会、さらには情報交換・ベンチマークの場として横のつながりができる場を設けさせていただいております。
そして、部会で共有された課題や問題に対する解決案や打開策を実践し、企業の垣根を超えてメンバー企業同士がさらに深堀り、共同研究を進めることで、企業の改善や方向性の策定にお役立ていただけるようにリサーチコミッティを設けています。
貴重な研究成果を生んだ「幸福度調査」

― TMJは、コーポレート機能協会のリサーチコミッティのひとつである「ニューノーマル時代の働き方研究委員会」に参画し、『【FY20幸福度調査&考察】現場改善による幸福度向上』の共同研究でご協力をさせていただきました(※2)。研究に対する反響はいかがでしたか。
TMJをはじめ本研究活動にてご尽力いただきました委員会メンバーやアンケートにご協力いただいた当会法人会員・メンバー企業の皆様のご協力により、幸福度調査ではこれまでにない大変興味深い結果が出ました。
今回の研究活動の指針となりました幸福学を研究されている前野隆司教授(慶應義塾大学大学院)へ結果をフィードバックさせていただいた際には、
「こういったコーポレート機能を担うスタッフ部門での研究はあまりなく、大変貴重な研究結果である」という、とてもありがたいコメントをいただくことができました。
今回の調査では、「定型の業務を担当している割合が高いほど幸福度が低く、業務改善を担当している割合が高いほど幸福度が高い傾向がある」という研究結果が出た一方、「定型業務の担当割合が100%の方々」よりも「定型業務の担当割合が70%で非定型業務の担当割合が30%の方々」の方が、「幸福度が低い傾向がある」という大変興味深い研究結果も出ました。
「こうあるべきだ、こうするべきだ」という認識の上で、調査・研究に基づいたエビデンス(根拠)があることで、皆様が自信をもって行動に移すきっかけとなり、広く世の中のコーポレート機能の改善に少しでもお役に立てればと思っております。
― コーポレート機能協会ではどんなテーマの部会を設けているのでしょうか?
コーポレート機能協会を設立させていただいた去年から、シェアードサービス(※3)をテーマとした部会を定期的に開催しています。
コーポレート機能協会という団体名の通り、当会はシェアードサービスに特化した業界団体というわけではありませんが、「シェアードサービス」はコーポレート機能における業務の集約化・可視化・標準化・効率化の視点から大変有効な経営手法のひとつであり、「シェアードサービス」における改革はコーポレート機能の改革そのものとなります。
現在の企業にはガバナンスの強化、リモートワークの推進や副業の認容など様々な形態の働き方の実現、ジェンダー・国籍・障害の有無に捕らわれない多様性の尊重、DX化・オートメーション化など多岐にわたる取り組みが求められています。シェアードサービスはそれらの課題に対しとても親和性が高く、大変相性の良い経営手法です。
シェアードサービスと本社機能は補完関係にあり、コーポレート機能という広い視点で見ると、シェアードサービスのあり方や役割がより明確になってきます。
今期は「シェアードサービス」をテーマとした各会合のほか、「監査役等研究部会(仮称)」や「業務改革研究部会(仮称)」などコーポレート機能に関し広くテーマを設定した部会を新設していきたいと考えています。
業務改革を後押しする「コミュニケーション」と「ファシリテーション」
― 新設を検討されている部会テーマの中で、「業務改革」がありましたが、幅の広い領域の中でどのようなものを想定されているのでしょうか?DXなのでしょうか。
業務改革についてこれまで色々な企業・コンサルタントなどの方々と意見交換させていただいたところ、業務改革を実現するには、「コミュニケーション」と「ファシリテーション(※4)」が大変重要であると感じています。

経理・人事・総務などの業務改革を行いたいと思った時、それらの業務に精通している方々が業務改革にも精通しているとは限りません。
業務改革を実現できる人材であることと、その対象業務に長けている人材であることとは、必ずしもイコールではないのです。
たとえば、コンサルティング会社の力をお借りして業務改革が成功しても、担当者の異動・転勤などによりその部署にノウハウとして残らなかったり、自発的に継続して業務改革を進めるナレッジ・スキル・文化がその部署で醸成されていない為、そのプロジェクト単発で終わってしまう部分があったりという課題があります。
そこで、継続的に業務改革を行う「業務改革人材」を育てるという観点から他社の業務改革事例やDX活用の成功・失敗事例などを比較・研究しながら、「コミュニケーション」と「ファシリテーション」などに着目した知見を溜めていける場を創っていただければと思っています。
― 「業務改革」というとDXの促進というイメージが強かったのですが、コミュニケーションという人特有のDXとは相反する部分からのアプローチに着目する部分が非常に興味深いです!
もちろん、基幹システムの刷新・見直し、新しいクラウド・ツールやシステムの検討・導入といったオートメーション化の視点は大変重要です。しかしそれ以上に、業務改革を成功させる企業は社内における「コミュニケーション」を大変重視しています。
社内において抵抗勢力やハレーション(悪影響)が生まれないように、プロジェクトを組む際は、組織を縦軸(機能・部署ごとに)捉えるだけではなく、横軸(機能・部署を超え横断的に)で考えています。当然、機能・部署の違いにより意見・考えの衝突は起こりますが、それを解決する大変有効な手法が「ファシリテーション」といえるのではないでしょうか。
― TMJは元々ベネッセコーポレーションの前身となる(株)福武書店の顧客サービスとマーケティング部門のシェアードサービス企業としての立ち上がり、BPOサービスを提供するというコーポレート機能協会の中では異質な存在かと思うのですが、協会において私たちにどんな貢献を期待されていますか?
 「事業継続」という視点から、お力をお貸しいただきたいと思っております。
「事業継続」という視点から、お力をお貸しいただきたいと思っております。
今回のコロナ禍で出社できないことで「給与計算が止まってしまうのではないか」、「取引先などへの支払いが滞ってしまうのではないか」などコーポレート部門のオペレーションの現場では様々な不安がありました。自社及び自社グループだけでなく、取引先各社にも大変な迷惑がかかってしまう事態が想定されたのです。
その最中、メンバー企業の皆様とお話をする機会をいただき、
「BPOの企業にお願いしていたので、業務を止めることならず大変助かった」
「コロナ禍にも関わらず大変強い責任感をもって業務を完遂していただけた」
などの声を多く聞きました。
自社1社(1か所)だけで抱えていると、業務が止まってしまうリスクがあるところ、TMJのようなパートナー企業と協力関係を持つことで事業継続という観点からリスクをヘッジする非常に強い力が発揮されると痛感しています。
また、BPOの企業としてクラインアンド各社から業務を幅広く受託する立場だからこそ見える部分が大変多くあるのではないかと思います。
どうしても自社でやっていることが当たり前だと思ってしまうことが多いですが、TMJがこれまでのご苦労された中で蓄積された経験やノウハウをもとに、企業が「通常」と思っている業務手法などが特殊であるという「気付き」を与えていただけるのではないかと期待しております。
<関連記事>緊急事態に備えて企業に求められるBCP(事業継続計画)の対応とは
― リサーチコミッティにおいて今後進めていく研究テーマなどあれば教えてください。
これまで様々な企業の方々と研究交流活動をご一緒いただいた中で、各社の導入システムや運用などに違いはあるものの、業務フローなど主要な部分に大きな違いはないことがはっきりしています。
そして、メンバー企業はじめ各社が試行錯誤をしている、課題とされる部分も大きくは変わらないこともわかっています。今後は、これまでの研究テーマを深堀りながらも、緊急度や重要度が高い課題とされているテーマを提案させていただき、メンバー企業間の強い連携のもと、自社・ご自身の課題解決の機会としていただきたいと思っております。
具体的には、「デジタル化やオートメーション化の調査・研究・推進」をテーマとした委員会を設けたいと考えています。ツールやシステムが次から次へと生まれ進化している中で、個社や個人で全てを継続的に網羅的に調べるのはどうしても限界があります。そこで、メンバー企業の有志の皆様に集まりいただき情報収集・情報共有ができる「場」があることで、世の中の最新トレンドをキャッチアップいただくなどお役に立ちたいと思っております。
企業が永続していくために必要なこととは
― それぞれが自分の領域を中心に見てしまう中で、横のつながりやコーポレート機能という視点に引き上げてもらえることで、また新しいアイデアや展開が生まれますね。
嬉しいご感想をいただき、ありがとうございます。経理や人事などといった機能で業務を分断せずに、一つの企業としてすべての業務がつながっていることが見えてくると、コーポレート機能を研究することは非常に面白くなってきます。
以前ある企画で、100年から250年以上に渡り、永く続く企業数社の代表経営者の方々に約1年間インタビューを続けたことがありました。その中で共通項として発見したことは、「創業以来の経営理念を頑なに守る」ことが必ずしも重要ということではなく、「その時代時代に合わせ、柔軟に変わり続けていく」ことこそが企業の永続につながっているということでした。今まさに大変革の時代、コーポレート機能にも当然同じことが求められています。
時には繊細に時には大胆に、特には慎重に時には勇気をもって大きく変わっていくことが企業に求められています。そのような中、判断や決断に迷いが生じた際に、当会が一助となればと心より願っております。
※1:海外視察では、BPO業務の多くを担う大連・無錫・蘇州・上海(中国)やホーチミン・ダナン・ハノイ(ベトナム)、グローバル企業のオペレーションの拠点であるクアラルンプール(マレーシア)やマニラ・セブ(フィリピン)、グローバル企業のオペレーションのオートメーション化が進むニューヨーク(米国)やロンドン(英国)など経理・人事・IT・営業サポート業務などのコーポレート機能の運営体制などを視察。
※2:TMJは、コーポレート機能協会のリサーチコミッティ(研究委員会)のひとつである「ニューノーマル時代の働き方研究委員会」に参画し、2021年1月中旬から2月の中旬にかけて、コーポレート機能協会に参加している31社の従業員509名を対象に、シェアードサービスで働く従業員の幸福度に焦点を当てた共同研究を実施しました。『【FY20幸福度調査&考察】現場改善による幸福度向上』の資料は<こちら>。
※3:シェアードサービス:「シェアードサービスとは、グループ経営の視点から、社内または企業グループ内で分散して行われている業務(経理や人事などの間接業務である場合が多い)を、①ある本社部門または子会社に集中し、②それが本当に必要な業務であるのか、または効率的なプロセスで行われているのか、という視点から業務の見直しを行い、さらに③業務を標準化して 処理を行うというマネジメントの手法である。」(園田智昭(2006).p.18 『シェアードサービスの管理会計』中央経済社.より引用)
※4:ファシリテーション:会議などの場で、参加者の発言や対話を促し、合意形成を促すサポートをする行動のこと。
キーワード
関連するサービス |
|---|